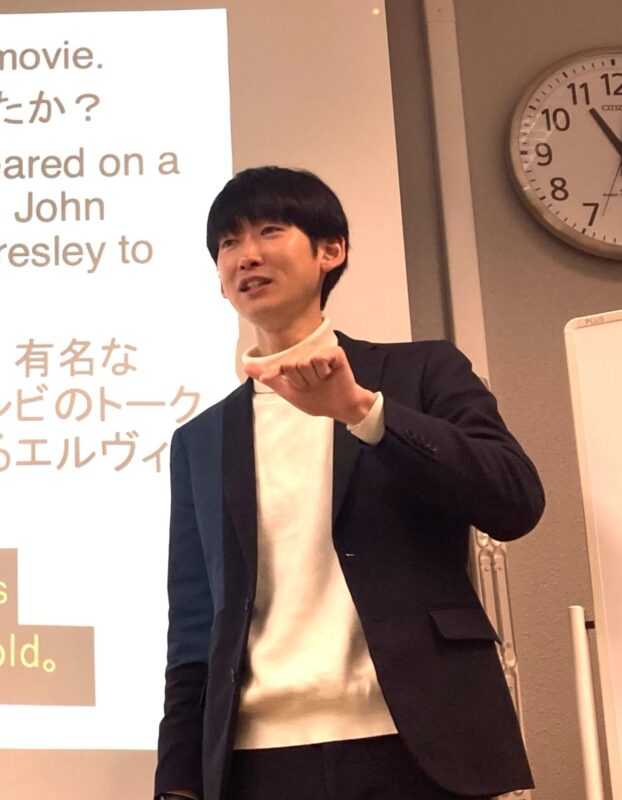インタビュー 田中豊大(たなかとよひろ)
先生のご専門は何ですか?
私は、主に聴覚障害者への英語教育について研究しています。本学の教員として勤務する前は、特別支援学校の教諭をしていました。生徒さんや保護者の方、先生方と過ごす中で、工夫を凝らしながら学び合ったり、協力して何かを成し遂げたりする経験ができ、多くのことを学ばせていただきました。現在の研究は、その延長線上にあります。
特別支援教育の視点は、共生社会の実現とリンクしています。障害児教育の歴史の中で積み重ねられた伝統あるノウハウと、日々進化する新しい考え方や知識、技術を組み合わせながら、一人一人にとって、より効果的で、分かりやすく楽しい英語の学び方・教え方について今後も深めていきたいと思っています。
新学部ではどのような授業を担当するご予定ですか?
共生社会創成学部では、語学教育科目である「英語A・B・C・D」(1年1学期~2年2学期)と障害社会学系科目である「専門英語1・2」(3年1・2学期)を担当する予定です。また、2~3年次に開講される「共生社会演習」や「共生社会創成プロジェクト実習」などのプロジェクト系科目も一部担当する予定です。いずれの科目も、聴覚障害学生と視覚障害学生が一緒に受講する科目です。
1~2年次に開講される「英語A・B・C・D」では、基本的な語彙や文法、表現の学びからスタートし、映画や映像などの動画教材を視聴して日常生活で頻繁に使われる表現を学んだり、英語で作成された資料やワークシートを使いながらペアやグループでディスカッションしたりする活動へと繋げていきます。受講生によって、英語の学習経験や習熟度がさまざまだと思いますので、学生同士の協働を通して、英語のタスクをクリアしながら,英語の総合的な運用力を高めていきます。
「専門英語1・2」は、3年次に開講される障害社会学系科目です。外国語の学習と科目やテーマの内容の学習を組み合わせて行うCLIL(内容言語統合型学習)という方法により授業を行います。つまり、共生社会について“英語で”学ぶことを通して、実践的な力を伸ばしていくことを目指した授業です。語学教育科目と比較すると専門性が高いですが、障害のある人の文化や情報保障、教育などをテーマとしますので、“自分事”として興味を持ちながら学ぶことができると思います。
共生社会創成学部の受験を考えている学生へのメッセージをお願いします
まずは、共生社会創成学部に興味を持ってくださり、ありがとうございます。受験生のみなさんは、これまでに障害のある当事者として、色々な思いや経験を積み重ねながら、今日まで生活してきたのではないでしょうか。「視覚に障害がある」「聴覚に障害がある」といっても、程度や特徴は十人十色ですし、歩んできた人生も一人一人異なりますので、みなさんのこれまでの軌跡を本当の意味ですべて知っているのは、みなさん自身だと思います。「こうしたら、うまくいった」ということだけでなく、「やってみたけれど、うまくいかなかった」という経験もたくさんあると思いますが、それらはみなさんにしか語ることのできない“強み”です。そして、現代社会の多くの場において、そういった当事者の実体験やアイデアが強く必要とされています。
共生社会創成学部での4年間の学びを通して、障害当事者であるみなさんが社会をよりよく変えていくために、“工夫のプロ”、“共生社会のリーダー”としての専門性を身につけ、社会に羽ばたいて行かれることを願っています。それが実現するように、私はみなさんに、“ことば”を学ぶことを通して、自分とは異なる文化を知り、世界中の人と繋がることの魅力について、心を込めて講義させていただきたいと思います。みなさんと一緒に学べる日を心待ちにしています。